

今日は深蒸し煎茶について勉強しましょう。

ずっと気になってたんですけど、深蒸し煎茶ってどうして渋くならないんですか?
・深蒸し煎茶の選び方
・深蒸し煎茶の淹れ方

いいところに気づきましたね。
実は製造工程の違いに秘密があります。
今日は深蒸し煎茶について学びましょう。
Contents
深蒸煎茶
深蒸し煎茶とは、殺青の蒸し時間が長い煎茶のことです。
蒸時間に決まりや基準はありませんが、およそ1分~3分ほど蒸しています。
煎茶は蒸し時間が長くなることで茶葉の組織が崩れやすくなり、お茶を淹れたときに濁りやすくなります。
見た目もよく、味もまろやかになることが深蒸し煎茶の特徴です。
この酸化酵素を失活させるために熱を加えることを【殺青】という。
日本では蒸すことによって殺青をしている
渋味を抑えるために生まれたお茶
深蒸し煎茶は、煎茶の渋みや苦味をもう少し抑えられないかと考えた末に生まれた製法です。
起源は諸説ありますが、牧之原台地の一帯で製法が確立されました。
現在の煎茶生産の主流であり、全国で広く作られています。
渋みはあまり感じられず、まろやかで飲みやすいのが人気の一つです。
なぜ渋みが少ないのか
深蒸し煎茶にはペクチンという物質が煎茶に比べて多く含まれています
このペクチンが渋みを抑える効果を発揮することがわかっています。
ペクチンは茶葉に熱を加えられた時に多く産出されます。
深蒸し煎茶の場合は通常の煎茶に比べて蒸し時間が長いため、ペクチンの含有量が多いのです。
ちなみに、カテキンやカフェイン量は普通蒸し煎茶と差はありません。
煎茶は殺青から最後の火入れ工程までずっと熱を加えられていますけど、その間にペクチンは増ないんですか?


殺青のための蒸し工程を終えた後の茶葉は、乾燥のために常に熱を加えられている状態です。
ただこの工程の間、茶葉自体の温度は37℃前後に保たれています。
ペクチンが発生するのはおよそ80~90℃の温度になるので、最初の蒸し工程より後では産出されないんです。
選び方
全国で広く生産されている深蒸煎茶ですが、いったいどれを選べばいいのかわからなくなると思います。
そこで、深蒸し煎茶の特徴を知って好みのお茶を探してみてください。
西日本か東日本でかなり大きく変わる
煎茶は産地によって味が全然違います。
特に西日本と東日本ではその味の差は
うま味がや甘味が欲しい時は西
西日本で作られているお茶は甘味やうま味を感じやすいです。
特に九州で作られているお茶は顕著に特徴がでます。
深蒸し煎茶の生産も多く、飲みやすいお茶が多いので煎茶を飲み慣れない人にもいいと思います。
僕がよく飲んでいたのは福岡県産の八女茶と鹿児島県の知覧茶です。


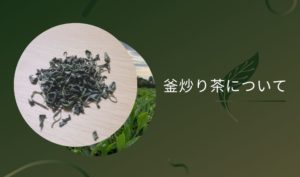





コメント