浅蒸し煎茶(普通蒸し煎茶)と深蒸し煎茶。
煎茶にもいろいろありますが、違いとは何なのでしょうか。
いつも飲んでいるお茶なのに意外と知らないお茶のこと。
深蒸し煎茶は煎茶の一つで、生産量もトップクラスのお茶になります。
製法は昭30年代ぐらいに確立されましたが、現在国内でお茶と言えば深蒸し煎茶と言っていいぐらい浸透しています。
味は渋味や苦味が少なくまろやかな口当たりです。
今日は深蒸し煎茶についてもう少し詳しく、淹れ方までじっくり説明いたします。
深蒸し煎茶
深蒸し煎茶とは、煎茶の蒸す時間が長くなったものをいいます。
煎茶は蒸し時間が長くなることで茶葉の組織が崩れやすくなり、お茶を淹れたときに濁りやすくなります。
お茶の透明度は低くなりますが、色合いは鮮やかになり、味もまろやかになることが深蒸し煎茶の特徴です
蒸時間に決まりや基準はありませんが、およそ1分、長いもので3分ほど蒸しています。
浅蒸し煎茶と深蒸し煎茶は、この蒸す時間が長いか短いかで、お茶の見た目や味わいが変わるという違いがあります。
渋味を抑えるために生まれたお茶
東日本のお茶は葉肉が分厚く苦味渋味が西日本に比べて強く出やすいという特徴があります。
お茶の盛んな静岡県でも例外ではありませんでした。
そこで煎茶渋みや苦味をもう少し抑えられないかと考えた末に生まれたのが深蒸し煎茶でした。
製法としては青殺の際、蒸し時間を長くするというものです。
こうすることによりお茶の組織はくずれてしまいますが、味はまろやかになり、渋味が抑えることに成功しました。
起源は諸説ありますが、昭和30年~40年の間に牧之原台地の一帯で製法が確立されたことが濃厚です。
深蒸し煎茶は現在の煎茶生産の主流であり、全国で広く作られています。
渋みが強くないため、子供でも飲みやすく多くの人に親しまれています。
殺青とは
お茶は摘まれるとすぐに、茶葉に含まれる酸化酵素の影響で酸化発酵をし始める。
この酸化酵素を失活させるために熱を加えることを【殺青】という。
日本では蒸すことによって殺青をしている
なぜ渋みが少ないのか
深蒸し煎茶にはペクチンという物質が煎茶に比べて多く含まれています
このペクチンが渋みを抑える効果を発揮することがわかっています。
ペクチンは茶葉に熱を加えられた時に多く産出されます。
ペクチンが発生する温度はおよそ80℃~90℃で青殺の時のみ生産されます。
深蒸し煎茶の場合は通常の煎茶が30秒~40秒の蒸し時間に対して、60秒~100秒と長くなります。
その結果ペクチンの含有量が多いのです。
ちなみに、カテキンやカフェイン量は普通蒸し煎茶と差はありません。
淹れ方
手順
①お湯を沸かす
②沸騰したら5分ほど沸かしす
③火をとめ、一冷ましし、80℃前後になるようにする
④急須に茶葉を2g~3g(ティースプーン山盛り1杯)か、カップであればティーパック1つ入れる
⑤お湯を急須なら6~7割、カップなら8割入れる
⑥30秒ほどしたら急須を振りながら少しずつ湯呑に注ぐ(下部動画参照)
⑦カップであれば、45秒ほどしてからティーパックを上下に振る
水出し茶の甘味がすごい
①お茶ボトルに10gの茶葉を入れる
②冷蔵庫で一晩おく
水出し煎茶はとても甘く、夏場におすすめです。
低温で抽出されることによって、腸内で働くカテキンの多く摂取できるようになるため、免疫力の向上につながります。
出来上がったお茶は、24時間以内に飲み切ることをお勧めします。
浅蒸し煎茶と深蒸し煎茶、あなたはどちら派?
浅蒸し煎茶と深蒸し煎茶は青殺の際の蒸し時間が違うだけでここまで違いが出るのかというほど味も見た目も変わってしまいます。
どちらも魅力的でおいしいお茶ですが、中にはどちらかを好んで飲まれる方もいらっしゃいます。
両方ともの違いを知ってあなたの好きなお茶を探す参考にしてください。
浅蒸し煎茶
見た目:水色は透明
色合い:薄い褐色~黄緑色の間ぐらい
甘味、うまみ、渋味、苦味、香りのバランスがよく、風味は透明感があり、植物由来の香りを感じやすい。
浅蒸し煎茶(普通蒸し煎茶)は香りのお茶
浅蒸し煎茶(普通蒸し)は香りとお茶本来の味を楽しみたい方にお勧めです。
渋味や苦味もありますが、生野菜を食べる感覚で素材本来の香りや味を楽しめるお茶です。
淹れ方によって味の変化が大きいのも特徴です。
お茶の品種や、生産地域の特徴も出やすいため、嗜好品としてお茶を愉しむ方にもおすすめです。


浅蒸し煎茶
深蒸し煎茶
深蒸し煎茶
見た目:水色は不透明
色合い:深い緑色
甘味やうまみを強く感じられ、まろやかな味わい。苦味と渋味は控えめ。
深蒸し煎茶は味のお茶
深蒸し煎茶は苦味、渋味が抑えられ、お茶が苦手な方も飲めるぐらいまろやかで飲みやすいです。
見た目もよく、色鮮やかな緑色をしているため、来客のお茶としても喜ばれます。
淹れる際のお湯の温度による味の差があまりないので、淹れやすいおちゃであることも魅力です。
味が安定しているため、子供でも飲みやすいお茶です。
地域による味の違い
深蒸し煎茶は浅蒸し煎茶(普通蒸し)ほど品種や産地の違いによる味や香りの変化はありませんが、
あまさやコクの強弱などは地域によって変化が見られます。
代表的な地域のお茶を紹介しますので、今後のお茶探しの参考にしてみてください。
狭山茶:埼玉県
狭山火入れで有名な狭山茶です。
茶葉に肉厚があり、深蒸し煎茶でありながらほどよく渋味が感じられる。
火入れの強さは昔ほどではないが、他の地域より香ばしさを感じられるのも特徴である。
掛川茶:静岡県
お茶どころの静岡県はどの地域のお茶も優れていますが、テレビ放送などでも注目された掛川のお茶を紹介します。
掛川茶は茶草場農法を採用している数少ない地域です。
自然と共存を目指した農法で、世界農業遺産にも登録されました。
そんな自然を大切にする農法がお茶の味にも現れています。
あまみ、コク、ほんのり渋味のあるお茶は、バランスの取れた味わいに仕上がっています。
霧島茶:鹿児島県
九州は鹿児島県、霧島のお茶を紹介します
霧島は宮崎県との県境にあり、少し山間の産地になります。
鹿児島県と言えば知覧茶が有名ですが、霧島のお茶も甘く透明感があり根強い人気を誇ります。
甘さに関しては、浅蒸し製法のものですら強烈で、深蒸しなった時の甘さは他の地域ではなかなか類を見ないほどです。
水出しにすればさらに強烈甘味が口いっぱいに広がります。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
現在最も多く生産されている煎茶がこの深蒸し煎茶であるため、見る機会はそれなりにあるかと思います。
たくさんの種類の中の一つであるということと、お茶を好きになるきっかけにするにもいいお茶ではないかと思います。
良くも悪くも個性が出づらいお茶ですが、飲み慣れてくれば産地や品種の違いも分かってきます。
子供も飲みやすいので、家族みんなで楽しむにもよいお茶だと言えます。
楽しいティーライフを。

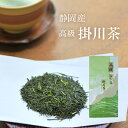















コメント