浅蒸し煎茶と深蒸し煎茶はどちらがおすすめ?
どの時期のお茶が一番いいの?
どこのお茶を選べばいいの?やっぱり静岡のお茶?
お茶淹れに慣れてきたときやお茶を買う時、悩まされること、ありますよね。
でも大丈夫です!
そんな悩みを解決していきましょう。
今日のお話
それではいってみましょう。
浅蒸し煎茶と深蒸し煎茶の好み分け
浅蒸し煎茶と深蒸し煎茶は全くタイプが別になります。

浅蒸し煎茶は嗜好品タイプの方
嗜好品タイプとは
浅蒸し煎茶(普通蒸し煎茶)は産地や品種、栽培方法による味や香りに大きな違いが生まれます。
植物が持つ本来の味や香り、これを滋味と言いますが、この滋味を楽しむことが好きな人は浅蒸し煎茶(普通蒸し煎茶)がおすすめです。
深蒸し煎茶は
深蒸し煎茶はとにかく飲みごたえ抜群で、お茶が好きな人におすすめです。
深蒸し煎茶は、品種や産地の違いがあまり強く出ません。
もちろん、飲み比べをすればわかりますが、それよりもごくごくといくらでも飲めてしまうところが魅力です。
しっかり満足させてくれるお茶になります。
どの時期のお茶を選べばいいの?
お茶の一番おいしい時期は新茶の時期である、4月~5月です。
例外的に3月や、6月に摘まれるお茶もありますが、4月~5月が一番多くお茶が出回ります。
新茶は味や香りがはっきりしている
お茶を飲まれるのであれば新茶がおすすめです。
旬のお茶であるため、価格も少し上がりますが、味や香りがはっきりしていて美味しいです。
飲み比べなどをする際も、違いがはっきり出るので勉強にもなります。
4月~5月ごろは全国のお茶屋さんで棚に並ぶため、すぐに手に入れることが出来ます。
また、冬場でも新茶として記載されているもの新茶になります。
お茶は劣化しづらいため、季節外れの購入でも春先と同じ味と香りが楽しめます。
どこのお茶を選べばいいの まずは西日本か東日本で選ぶ
お茶を選ぶとき、どこの地域のお茶がいいのか悩むことがあります。
そこでまず考えるのが、西日本のお茶か東日本のお茶かということです。
西日本のお茶は甘やうまみ
西日本のお茶は気候の関係で、葉肉が薄く、甘味やうまみがわかりやすい傾向になります。
有名な産地で言えば、宇治(京都)をはじめ、知覧(鹿児島県)や八女(福岡県)など名の知れた産地が豊富にあります。

私がお茶を勉強しシ始めたころによく飲んでいたのは八女茶(福岡県)でした。
素人の私でもうま味や甘味を出しやすくとても飲みやすいですし、お茶を淹れる練習にもすごくいいお茶でした。
東日本のお茶は渋味が強い

東日本は気候の関係で、茶葉の葉肉が厚く滋味も強く感じる。
静岡県全域を初め、狭山(埼玉県)や抹茶で有名な西尾(愛知県)などこちらも名だたるお茶が顔を揃えます。
静岡県の山間部のお茶は今でもよく飲用します。
川根茶や天竜茶など、少し価格は上がりますが、透き通るような味と香りはとても印象深いです。
どしっと重たいお茶であれば狭山茶(埼玉県)がおすすめです。
しっかりと渋味が利いたお茶好きにはたまらない味です。
なぜ地域で葉の形状に差が出るのか
植物には光合成という太陽の光を浴びることで行われる代謝運動があります。
この代謝は基本的には春先から初秋ぐらいにかけて行われ、冬を越すために必要なエネルギーを蓄えます。
そのエネルギーの代謝運動の速さは、気温によって大きく変わります。
気温が高いと早くなり、低いと遅くなります。
代謝が遅くなった葉には、代謝物として生まれた糖の流れが遅くなるため、それが葉に蓄積して葉肉が厚くなります。
日照時間が長いと茶葉がどんどん成長するため、葉が大きくなります。
西日本と東日本では、気温の差、太陽の動き、日照時間が異なってきます。
太陽は東から西へと動き、気温は東の方が寒冷であるため、活発に光合成を行える時間が西に比べて少なくなるため、少しでも多く代謝エネルギーを作り出すために、葉肉が厚く、茶葉も小さくなる傾向があります。
もう一つ、こちらは諸説ありますが、雪の降る地域では積雪に耐えるために茶葉や枝が少し大きくなる傾向にあります。
この差は同じ県内でも見られる
寒暖差による茶葉の形状の違いは、同じ県内であっても発生する事例です。
例えば静岡県であれば、平地である牧之原や掛川と、山間部である川根や本山とでは葉肉の厚さや、葉の大きさが違います。
特に山間部は気温も低く、場所によっては日照時間が極端に少ないため、葉肉は厚くなりますが葉があまり大きくならない傾向があります。
こうした特徴の差は、各都道府県で見られます。
お茶選びに慣れてきたら、同じ県内で比べてみると面白いです。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
お茶は地域により味や香りが変わりますが、大きく分けると西日本と東日本でも大きく変わります。
もちろん、品種や生産者のこだわりによるところが一番大きいので、お茶に慣れてきたころはそちらを意識していきたいところです。
でもまずは、何県のお茶と何県のお茶を飲み比べてみる、ここから始めるのが楽しいです。
とにかくたくさんの地域のお茶を飲んでみましょう。
それでは素晴らしきティーライフを。
お茶の福袋









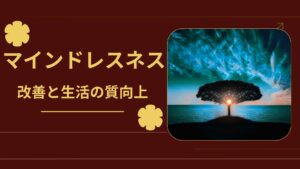


コメント