お茶に興味をお持ちのあなたへ
カテキンとタンニンっていったい何が違うのか、気になりますよね?
答えはどちらも同じ【渋味成分】です。
ではなぜ【お茶のタンニン】と【お茶のカテキン】二つの呼び方があるのでしょうか?
この違いは何のかをお話しします。
タンニンとカテキンの違い
お茶の渋み成分と言えば【カテキン】ですし、渋味と言えば【タンニン】というイメージがあります。
実は【タンニン】とは渋味の総称のことを言います。
そもそも【タンニン】の上に【ポリフェノール】という大きなくくりがあります。
ポリフェノール→タンニン→カテキン
こんな感じです。
【カテキン】という呼び名は、より具体的な言い方だということになります。
つまり、ポリフェノールの中にタンニンがあって、その細かい成分にカテキンがあるといったイメージです。
例を挙げると、飲み物中にお茶があって、お茶の中でも紅茶や緑茶に分かれるといった感じでしょうか。
なので【タンニン】も【カテキン】も同じ渋味を表す言葉なのでどちらも正解ではあります。
ただ、お茶の話をする際は【緑茶カテキン】の話がよく出ますので、【カテキン】の方がかっこがつくかもしれないです。
渋味がカテキンではなくタンニンと呼ばれる由来
皮製品を使ったことがありますか。
この皮を加工する、つまり「皮を鞣す(なめす)」時にタンニンは使われていました。
動物の皮はそのまま使えば腐ってしまうし、乾かして乾燥させると硬くなってしまい、とても使えるものではなくなります。
そこで「鞣す」、つまり柔らかくするという工程が入るのです。
その時に植物の渋み成分「タンニン」が使われていました。
このことから植物の渋味成分=「タンニン」となっていったと言われています。
タンニンは抗菌作用を有することから、革製品の耐久性や保存性を大きく向上させる役割があります。
この知識や技術が古代エジプトから知られ、行われていたという経緯には驚きが隠せません。
その加工法は現在でもしっかりと残っています。
ただ、日本で鞣す工程に使われている植物は「ミモザ」です!
お茶ではないんですね(笑)
ミモザのタンニン
ミモザに含まれるタンニンは【エラジタンニン】といい、緑茶のカテキン類とは異なるタンニンが含まれています。
この【エラジタンニン】も収斂性(渋味を口内で感じたときのざらっとした感触)や抗菌抗炎作用と、他のタンニンに見られる効果効能を有します。
なぜミモザのタンニンが選ばれるのか
【エラジタンニン】は水溶性で使いやすく、他のタンニンより皮の加工に向いているという特性があります。
革製品に与える影響としては、色合いが均一になり高級感を出せることです。
耐久性も向上することから、長く使っても型崩れしにくい革製品が出来上がります。
ミモザの効能
ミモザは食用にも工業用にもなる万能な植物です。
そんなミモザは私たちの身体にも好影響を与えてくれます
ハーブティはよく飲まれているお茶です。
効能
ミモザはハーブティとしてよく飲まれていますが、アロマなど香りをかぐことでも効果を発揮します。
アロマを使用する際はラベンダーやカモミールと併用するとリラックス効果や抗炎症効果を強めることができます。
タンニン、渋みが苦手な方へ
お茶は飲みたいけど、渋いのが苦手、、そんな方、意外と少なくありません。
そこで、この渋味について二つ知っておいてほしいことがあります。
これを知れば渋味が好きになるかもしれません。
1・渋味はもともとみんな苦手?
知ってほしいこと1つめは
実は渋味を含めお茶の味というのは、後天的に好きになる味なのです。
お茶を最初は全く飲めないという人も中にはいるようで、そんな人が少し飲みなれてくると逆に好きになるということがよくあります。
渋味に関しては特にそうで、最初は新茶の柔らかい味が好きだったのが、飲んでいくうちに渋みがくせになるってくる人が後を絶ちません。
これを【acquired taste:アクイワード・テイスト(後天的な嗜好、嗜好の変化、後々好きになっていくこと)
と呼びます。
なぜ渋味が後から好きになる?
実は、人間の体の構造上、味覚における苦味や辛味などは身体に影響が出るものとして本来は拒絶するようになっています。
特に子供のころは自らを守るためにより敏感に感じやすく、その結果苦いものはまずい、辛いものは危ないというように記憶するのです。
年齢を重ねるとともに緩和され、徐々に体がなじんでいくので後天的に苦味や辛味もおいしく感じてきます。
渋味もその一つだというわけです。
ですから、渋いのが苦手だからと言わず、いろんなお茶を飲んでみてください。
渋味克服法1・渋味の少ないお茶を飲む 新茶や玉露
渋味の基となるカテキンは、お茶が成長する過程で光合成を行った結果、テアニンといううまみ成分が変化して生成されます。
つまり、お茶が成長して間もない時期に摘まれた新茶や、光合成をさせないように栽培された玉露や抹茶には
渋味の基であるカテキンが少ないのです。
抹茶はテイストが違うので参考にならないかもしれませんが、4月から5月に売り出される新茶を飲めば少しずつ渋味が克服できるかもしれません。
お茶はお湯の温度を70℃前後で淹れたうまみを重視したものが好ましいです。
下記記事のうまみを重視した淹れ方を参考にしてください。
2・渋味ではなくえぐみだった
そもそもその渋味、本当に渋味ですか?ってことです。
え?と思われた方、正解です。え?ですよね(笑)
渋味と一言で言われても、実際渋味がわからない方も多いです。
私も最初そうでした。
実は渋味によく似た感覚で、【えぐみ】というものがあります。
これは、舌先からびりびりと嫌な感覚があり、非常に気持ち悪いです。
もしかしたらそれは渋味ではなくてえぐみかもしれません。
えぐみであれば私も苦手です。
渋味とは本来感覚的には気持ちいいものです。
お茶淹れに失敗するかお茶の製造に無理が生じる、いわゆる欠点茶というものの中に、強いえぐみを持つお茶があります。
そういったお茶を熱湯で無理やり淹れると抽出されやすいです。
お茶淹れの際、なるべくお湯の温度管理をしっかり行い丁寧にすればえぐみが出ることはほとんどありません。
逆に渋味が好きな人向けのお茶
番茶一択です
渋みのもととなるカテキンは、冬に近くなればなるほど含有量が増していきます。
そのため、秋番茶や秋冬番茶と呼ばれる番茶はカテキンが豊富です。
これぐらいの番茶になるとカフェイン含有量も少なくなり、熱めのお湯で淹れても苦くなりにくいです。
なにより最高に渋いお茶が淹れられることと、栄養成分としても優れたカテキンがたくさん摂取できるという
いいことづくめのお茶なのです。
番茶について詳しくは下記の記事を参考にしてください。

終わりに
いかがでしたか?
【タンニン】と【カテキン】
お茶に関しては、緑茶タンニンとか言わないのでカテキンで統一していいと思います。
たまにタンニンと言われる人もいますけど、言葉は悪いですが昔の人は結構多いかもしれないですね。
どちらも渋味のことを指しているので、それさえ覚えておけば特に問題はないです。
あと、味わいとしての渋みも是非慣れてください。
どうしても苦手な方もいるので無理強いはしませんが、
渋味が活きるお茶も存在します。
そんなお茶の渋みの気持ちよさは本当に記憶に残るものです。
とにかくいろいろなお茶、いろんな人のお茶を飲んでみることをお勧めします。
楽しいティーライフを。
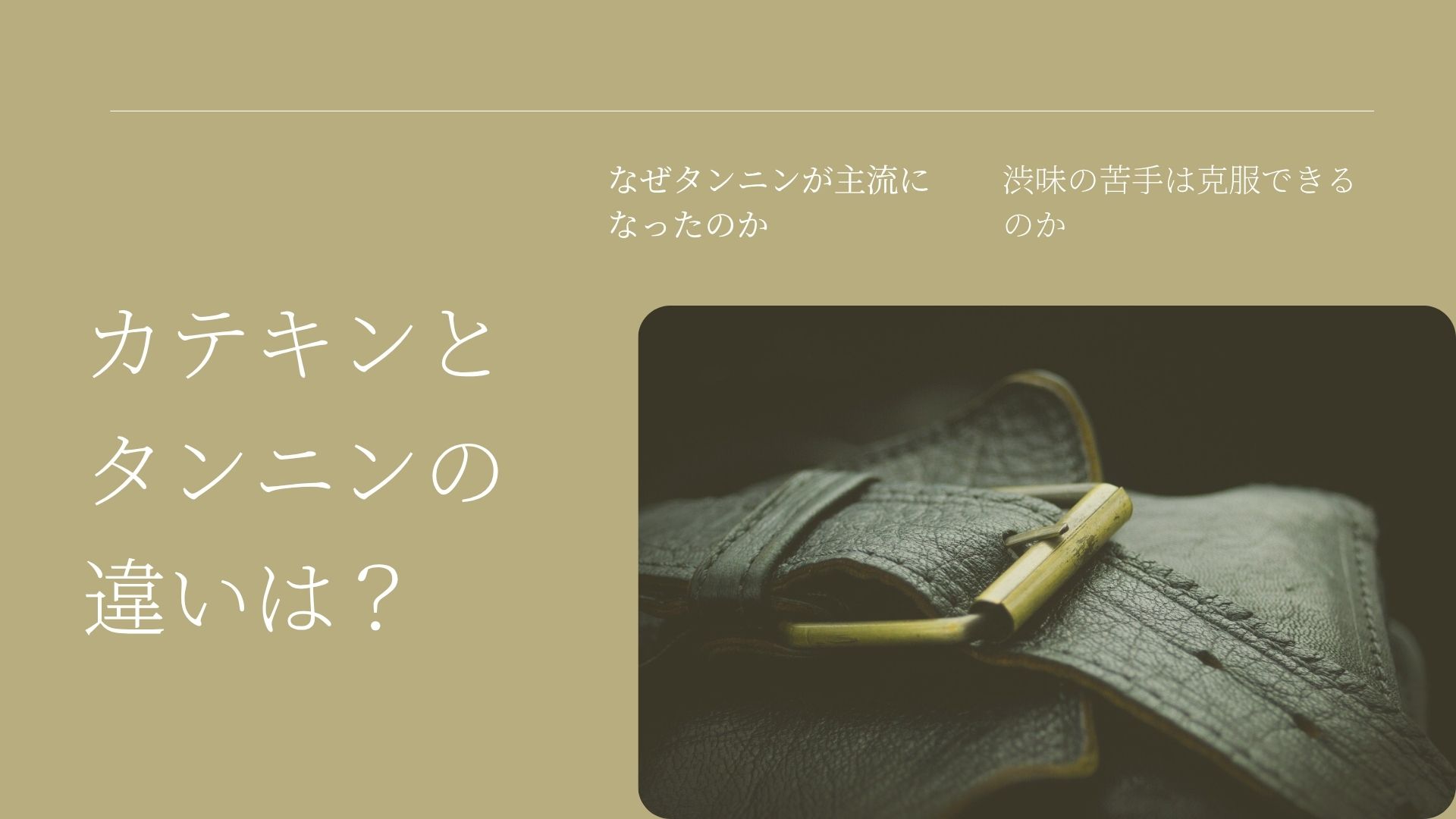


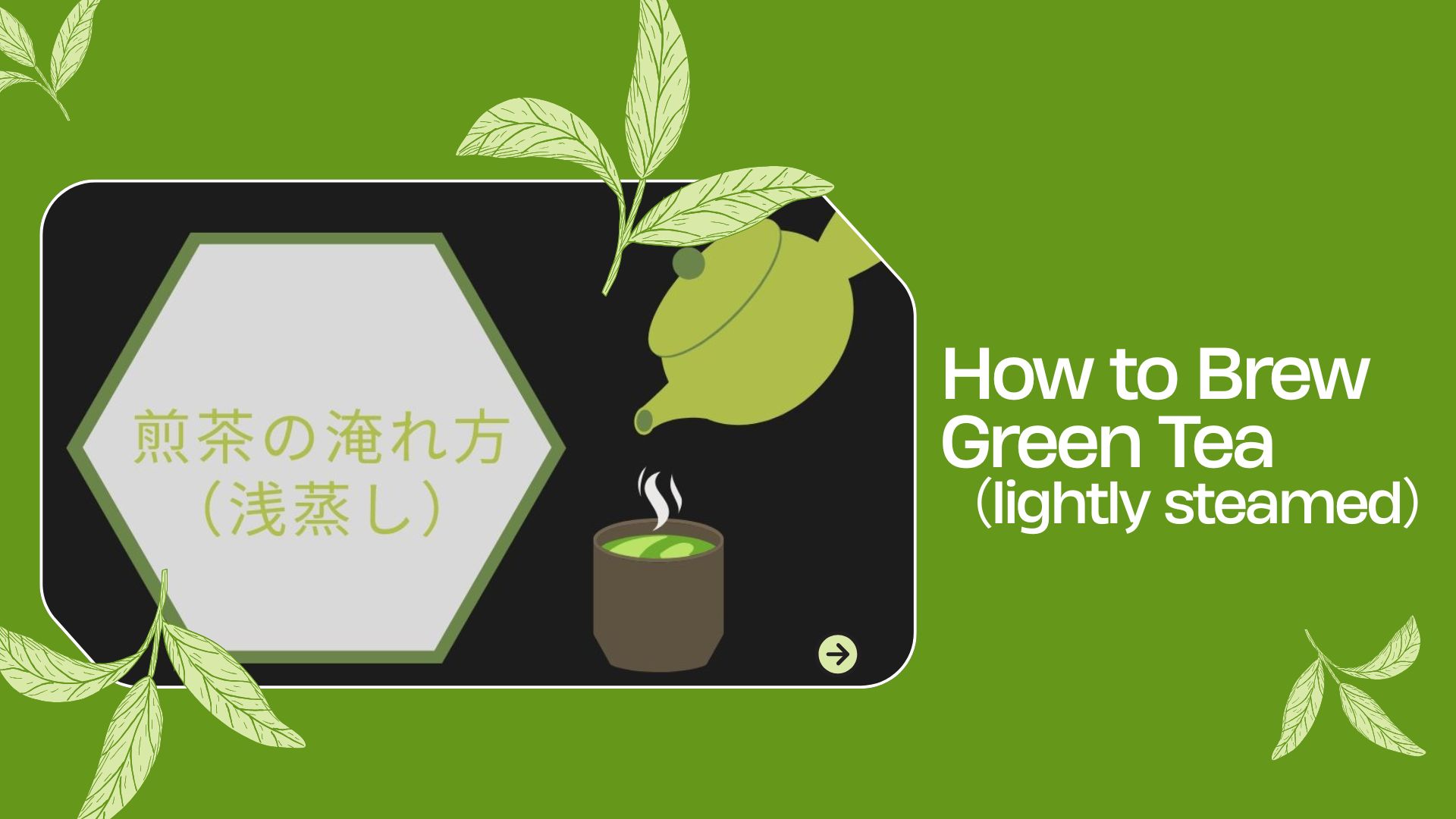







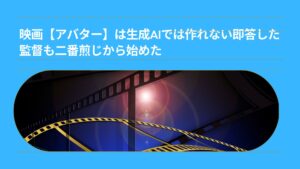
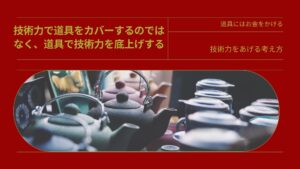


コメント